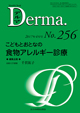イチからはじめる美容医療機器の理論と実践 改訂第2版 宮田成章/著
ISBN:978-4-86519-281-0 C3047
定価:7,150円(税込み)
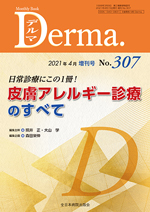
日常診療にこの1冊!皮膚アレルギー診療のすべて<増刊号>
森田 栄伸/編
978-4-86519-639-9 C3047
2021年4月
de0307

定価6,380円(税込み)
食物アレルギー、薬疹、接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、蕁麻疹といったアレルギー性疾患の診療のポイントや新しい考え方を詳説。プロアクティブ療法のコツやパッチテストの活用法、薬剤リンパ球刺激試験の実際や学校生活管理指導表の書き方まで、実地診療に役立つ内容が盛りだくさんの1冊です!
| Ⅰ.食物アレルギー | |
| 食物依存性運動誘発アナフィラキシーの診断と予後 | 濱田 祐斗 |
| 食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)の診断・管理については基本的な事項を中心に,予後については成人におけるFDEIAの代表であるWDEIAに関する近年の報告をまとめた. | |
| PFASの病態と診断の進め方 | 福冨 友馬 |
| 我が国では,PR-10,profilin,GRPがPFASの三大アレルゲンである.原因アレルゲンにより,発症の原因となる花粉,交差反応を示す食物,誘発症状が異なっている. | |
| 魚アレルギーとアニサキスアレルギー | 千貫 祐子ほか |
| 魚類摂取後のアレルギー症状では,魚アレルギーのほか,アレルギー様食中毒やアニサキスアレルギーを鑑別する必要がある. | |
| α-Gal syndromeとpork-cat syndrome | 千貫 祐子ほか |
| 本邦における獣肉アレルギーの主なものにはα-Gal syndromeとpork-cat syndromeがあり,いずれも感作経路の対策を行うことによって治る可能性がある. | |
| 食物アレルギー患者が注意すべき薬剤 | 下条 直樹 |
| 食品成分は,薬剤の主剤である場合と賦形剤・添加物として用いられている場合がある.食物アレルギー患者に使用できない「禁忌」の表示があってもわかりづらいものや,そもそも「禁忌」の記載のない医薬品が少なくない.個々の薬剤についての確認が最も重要である. | |
| Ⅱ.薬 疹 | |
| 薬疹の病型と皮疹の見方 | 橋爪 秀夫 |
| 多形紅斑とスティーブンス・ジョンソン症候群,播種状紅斑丘疹の違いと新しい薬疹病型を理解し,正しい薬疹の臨床病型の理解につなげる. | |
| SJS/TENの疫学 | 末木 博彦 |
| SJS/TENの第2回全国疫学調査結果を概説した.前回と比べTEN患者の平均年齢が6.6歳上昇し死亡率が10%上昇した.年齢や基礎疾患に応じた治療が課題である. | |
| SJS/TENの診断 | 渡辺 秀晃 |
| SJS/TENの診断において,特にSJSと多形紅斑重症型との鑑別が難しい.臨床症状や病理所見を含めて詳しく概説し,新しい診断基準の理解を深める一助としたい. | |
| SJS/TENの病態と治療 | 濱 菜摘ほか |
| SJS/TENの細胞死はアポトーシスとネクロプトーシスが混在している.様々なバイオマーカー研究が進行しており,本邦ではステロイド全身療法やIVIg療法などで治療されている. | |
| DiHSの診断におけるバイオマーカー | 浅田 秀夫 |
| DiHSの病初期では,他の薬疹や中毒疹との鑑別に悩まされることが多い.血清TARCがDiHSの急性期に特異的に上昇することから,早期診断マーカーとして期待されている. | |
| DiHSの治療―重症度分類から考える― | 水川 良子ほか |
| DiHS/DRESSの重症度を発症早期から判断し,ステロイドの適応を含めた適切な治療を行う.重篤な合併症や致死的になり得るCMV再活性化を予測し,治療介入を速やかに行うことも重要である. | |
| 重症薬疹の遺伝的背景の最新知見 | 莚田 泰誠 |
| 薬疹の発症リスクに対する特定のヒト白血球抗原(HLA)アリルの影響は極めて大きく,事前のHLA検査によって薬疹の発症を回避することが期待されている. | |
| 重症薬疹の肝障害 | 小林 宗也ほか |
| 胆管消失症候群(VBDS)は,後天的な原因により組織学的に小葉間胆管の破壊,消失を認め,慢性の胆汁うっ滞をきたす病態である. | |
| 重症薬疹の肺障害 | 金子 美子 |
| SJS/TEN合併閉塞性細気管支炎は多彩な臨床経過を示し,皮膚病変が軽快しても慢性に悪化進行し呼吸不全に至る重篤例があり,内科医との連携が重要である. | |
| Ⅲ.接触皮膚炎 | |
| 接触皮膚炎の発症機序 | 相場 節也 |
| 接触皮膚炎のメカニズムの解析は,アトピー性皮膚炎や他のアレルギー性疾患の病態の理解にもつながる. | |
| パッチテストの実際と応用 | 関東 裕美 |
| 接触皮膚炎を疑ったら原因検索を積極的に行うが,検査は感作リスクがあることを念頭に置く必要がある.適切な症例を選択して日常生活指導に役立つような検査を計画する. | |
| パッチテストパネル®(S)の活用法 | 矢上 晶子 |
| パッチテストパネル®(S)(佐藤製薬)は,簡便かつ安全にパッチテストが実施できる.各試薬の特性や含有製品,生活指導について概説した. | |
| 金属アレルギーの診断 | 足立 厚子 |
| 金属アレルギーには金属接触アレルギーと全身型金属アレルギーがある.前者の診断にはパッチテストが第一選択であるが,後者の診断にはパッチテストのみでは不十分である. | |
| 最近話題の接触アレルゲン | 高山かおる |
| 接触皮膚炎の注目アレルゲンとしてニッケル・金といった金属,ゴムの加硫促進剤,防腐剤,染毛剤,局麻剤,新たな医療機器の粘着剤などを取り上げ解説する. | |
| Ⅳ.アトピー性皮膚炎 | |
| アトピー性皮膚炎の発症機序 | 古江 増隆 |
| アトピー性皮膚炎の表皮バリア障害は,IL-13/IL-4―Janus kinase―signal transducer and activator of transcription 6(STAT6)/STAT3軸がaryl hydrocarbon receptor(AHR)―(OVO-like 1)軸を抑制するために発生し,アトピー性皮膚炎の治療薬はそれを阻害,あるいは回復させる. | |
| 乳児アトピー性皮膚炎と食物アレルギー | 福家 辰樹 |
| 乳児アトピー性皮膚炎のフェノタイプ分類や持続リスク,早期介入寛解維持による食物アレルギー発症のリスク低減効果,保湿剤によるアトピー発症予防研究についてまとめた. | |
| 治療ゴールを目指したアトピー性皮膚炎の治療―プロアクティブ療法のコツ― | 片岡 葉子 |
| プロアクティブ療法の理論は平易であるが,確実な実践には治療者の技量や訓練が必要である.本療法を成功させるためのコツを15項目に分けて詳説した. | |
| アトピー性皮膚炎に対するデュピルマブの効果的な使用法 | 佐藤 伸一 |
| デュピルマブは単なる抗炎症薬ではなく,皮膚バリア機能を是正する作用を有するため,再燃を未然に防ぐプロアクティブ療法に最適である. | |
| Ⅴ.蕁麻疹 | |
| 慢性蕁麻疹の病態の新たな展開 | 柳瀬 雄輝ほか |
| 慢性蕁麻疹の発症・増悪における血液凝固系や補体系の役割はこれまでほとんど知られていなかったが,最近の基礎研究を通して,それらの重要性が明らかになりつつある. | |
| 慢性蕁麻疹に対するオマリズマブの適応と効果 | 織田 好子ほか |
| オマリズマブは多くの慢性蕁麻疹に対し効果的であることはよく知られているが,治療反応性には多様性があり,それらを予測する因子が様々報告されている. | |
| アスピリン蕁麻疹の診断と対応 | 福冨 友馬 |
| NSAIDsで誘発もしくは増悪する蕁麻疹は,大きく3つに分類できる.①皮膚型NSAIDs不耐症,②NSAIDsに対するIgE機序のアレルギー,③食物アレルギーがNSAIDsにより誘発されたものである. | |
| コリン性蕁麻疹と発汗障害 | 水野真由子ほか |
| 汗アレルギー型コリン性蕁麻疹,毛包一致型コリン性蕁麻疹,減汗性コリン性蕁麻疹/特発性後天性全身性無汗症の病態,鑑別のための問診,検査について解説. | |
| 遺伝性血管性浮腫の臨床 | 齋藤 怜ほか |
| C1-INHに異常があるHAE 1/2型では,診断が確定すれば対症療法ながら治療が確立されている.しかし,HAE 3型の病態には不明な点が多く,その病態や治療の有効性について解明が待たれる. | |
| Ⅵ.検査と管理 | |
| 特異的IgE抗体検査 | 辻 元基ほか |
| アレルゲンコンポーネントはうまく活用すれば,精度の高い診断が可能だが,特異的IgE抗体検査の原理を理解することが前提となる. | |
| 薬剤リンパ球刺激試験のとらえ方 | 高橋 勇人 |
| 薬剤リンパ球刺激試験は薬剤特異的T細胞を検出する検査である.様々な要因が検査結果を左右するため,検査の特性をよく理解したうえで,結果を解釈することが求められる. | |
| 学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の作成法 | 石黒 智紀ほか |
| 2019年に改訂された「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」と「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」から,生活管理指導表の記載のポイントをまとめた. | |
足爪治療マスターBOOK 高山かおる・齋藤 昌孝・山口 健一/編
ISBN:978-4-86519-280-3 C3047
定価:6,600円(税込み)
図解 こどものあざとできもの―診断力を身につける― 林 礼人・大原國章/編
ISBN:978-4-86519-276-6 C3047
定価:6,160円(税込み)
イチから知りたいアレルギー診療―領域を超えた総合対策― 大久保公裕/編
ISBN:978-4-88117-093-9 C3047
定価:5,500円(税込み)
Monthly Book Derma(デルマ) 229日常皮膚診療に役立つアレルギー百科<増刊号>戸倉 新樹/編
ISBN:978-4-88117-892-8 C3047
定価:5,940円(税込み)
Monthly Book Derma(デルマ) 296“中毒疹” 診断のロジックと治療阿部理一郎/編
ISBN:978-4-86519-628-3 C3047
定価:2,750円(税込み)
Monthly Book Derma(デルマ) 289知らぬと見逃す食物アレルギー矢上 晶子/編
ISBN:978-4-86519-621-4 C3047
定価:2,750円(税込み)
Monthly Book Derma(デルマ) 256こどもとおとなの食物アレルギー診療千貫 祐子/編
ISBN:978-4-88117-919-2 C3047
定価:2,750円(税込み)
Monthly Book ENTONI(エントーニ) 254口腔アレルギー症候群―診断と治療―白崎英明/編
ISBN:978-4-86519-548-4 C3047
定価:2,750円(税込み)