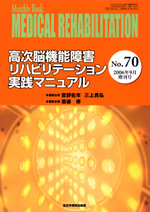
高次脳機能障害リハビリテーション実践マニュアル<増刊号>
渡邉 修/編
978-4-88117-320-6 C3047
2006年9月
mr0070

定価5,238円(税込み)
3営業日内ですぐに発送!
| I.疾患別高次脳機能障害のみかた―評価方法とその解釈― | |
| 脳梗塞・脳出血(右大脳半球損傷) | 石合 純夫 |
| 右半球の脳卒中後に起こる無視症候群のうち,最も頻度の高い半側空間無視はリハビリテーションの重大な阻害因子である.BITや日常場面の観察などで適切に評価することが大切である. | |
| 脳梗塞・脳出血(左大脳半球損傷) | 大沢 愛子ほか |
| 左大脳半球病変によって生じる高次脳機能障害について解説を行った.一般的に優位半球といわれる左半球の損傷では,多彩な神経心理学的症状を呈し,病巣や支配血管についても,幅広い知識が必要である. | |
| くも膜下出血 | 片桐 伯真 |
| くも膜下出血は,脳血管障害のなかでも多彩な高次脳機能障害を呈し,退院後の生活で問題となる.ここではくも膜下出血の概要とそれに伴う高次脳機能障害の特徴ならびに社会参加に向けた対応などを概説する. | |
| 脳外傷 | 橋本 圭司 |
| 脳外傷による高次脳機能障害は,外見からは複雑で理解しにくいことが多い.したがって,それらの問題を正しく評価し,より基本的なものから順序立ててアプローチすることが必要である. | |
| 低酸素脳症 | 渡邉 修 |
| 低酸素状態にさらされたとき,脳はどのように反応するのか.その後遺症にはどのような症状がみられるのか.その評価はどのように行うのか. | |
| パーキンソン病・脊髄小脳変性症 | 橋本 昌也ほか |
| パーキンソン病,脊髄小脳変性症の病像や背景,診断のポイントについて解説するとともに,発展のめざましい核医学的診断技術についても紹介する. | |
| 脳腫瘍 | 所 和彦 |
| 良性脳腫瘍の高次脳機能障害を含むリハビリテーションは脳血管障害のリハビリテーションのノウハウで対処が可能である.悪性腫瘍は再発のリスクが高く,耐久力を維持して早期の自宅復帰を目指すことが肝要である. | |
| アルツハイマー型痴呆 | 品川俊一郎ほか |
| アルツハイマー病の診断においては記憶障害や視空間認知・構成障害,見当識障害といった特徴的な臨床症状を正確に把握することが大切である. | |
| 脳性麻痺・二分脊椎 | 栗原 まな |
| 小児の高次脳機能障害のなかから生まれつきの障害(発達障害)に伴ったものについて述べる.脳性麻痺に伴う視覚認知障害と,二分脊椎(水頭症に由来)に伴う非言語性認知障害を紹介する. | |
| 自閉症・ADHD | 熊谷 恵子 |
| 自閉症・ADHDは,特殊教育から特別支援教育への移行に当たって教育のなかでもトピックの1つとなっている.自閉症は自閉症スペクトラムという考え方や心の理論の課題,ADHDは実行機能障害ととらえられてきたことに触れている. | |
| II.各症候に対するリハビリテーションの実際 | |
| 注意障害 | 中島 恵子 |
| 注意障害へのリハビリテーションとして,注意機能への直接的訓練である領域特異的訓練と社会的気づきを高めるために意識に焦点を当てた注意訓練を紹介する. | |
| 失語症 | 道関 京子 |
| 全体構造法は,失語症者の知覚階層に合わせた刺激要素を調えていくという理論的根拠を踏まえて施行されなければ,開発された具体的手段のみ真似ても有効な結果を生み出せない. | |
| 半側空間無視と関連障害(Pusher) | 網本 和 |
| 半側空間無視とその関連障害であるPusher現象に関して,病態とリハビリテーションアプローチについて概説した.半側空間無視については,感覚運動可塑性刺激であるプリズムアダプテーションを中心に述べた.Pusher現象については,病巣に関する知見とメカニズムに言及した. | |
| 記憶障害 | 種村 留美ほか |
| 記憶障害者でも保たれやすい記憶を活用して誤りなし学習,PQRST法,視覚イメージ法,展望的記憶訓練が開発され,効果をあげている. | |
| 行動障害 | 阿部 順子 |
| 意欲・発動性の低下や感情コントロールの低下などの行動障害に対しては,早期から環境を調整し,行動を管理する方法を学んでいけるようにアプローチしていくことが重要である. | |
| III.リハビリテーション手技の工夫 | |
| 重度失行症例へのアプローチ | 原 寛美 |
| 左下頭頂小葉病変により生じることの多い観念失行に対して,その的確な評価に依拠し,ADL訓練にはerrorless completion of the whole activitiesなどのデザインされた手法を導入することが有用となる. | |
| 脳梁離断症候群を呈した脳梁梗塞の1例 | 佐々木信幸 |
| 脳梁部分梗塞により脳梁離断症状を呈した.視覚フィードバックや協調動作訓練を行ったが,左上肢失行は残存し対症手段も要した.左下肢も言語に対する反応性低下を認めたが,早期に改善した. | |
| 外傷性脳損傷者のリハビリテーション実践―ドリル学習などの効果性― | 藤井 正子ほか |
| 外傷性脳損傷後に起こる高次(脳)機能障害へのドリル学習の効果は,注意障害や記憶障害が改善する.代償的訓練よりも復帰的訓練,支援より訓練がポイント. | |
| 脳外傷者のリハビリテーションにおける理学療法の視点 | 森田 智之ほか |
| 脳外傷者のリハビリテーションはチームアプローチが重要である.そのなかで理学療法士は運動を通して対象者の評価と治療を実施しながら,行動観察を行うことが重要である. | |
| 自閉症を有する方への就労支援―構造化したアプローチとジョブコーチによる支援― | 川邊 循 |
| 自閉症を有する方への就労支援では,ジョブコーチによるご本人のアセスメントから職場開拓,職場での支援,アフターフォローまでの一貫した支援が有効と考える. | |
| 認知症患者に対する通所リハビリテーションの経験 | 山内 寿恵ほか |
| 通所リハビリテーションでは認知症患者の生活機能を維持,改善するために周辺症状である「行動・心理徴候」の原因を除去し,中核症状にアプローチする. | |
| IV.最新の研究 | |
| 高次脳機能障害者に対する認知運動療法の効果 | 池田 由美ほか |
| 認知運動療法の基本概念について概説し,高次脳機能障害のなかでも失行症を取り上げて,その病態の解釈と治療方法略について紹介した. | |
| 失語症の回復 | 安保 雅博 |
| 失語症の回復を評価する方法の1つとして,脳機能画像がある.極めて有効な方法であるが,いろいろなバイアスがかかるため諸説の意見がある. | |
| 手の心的回転における脳内情報処理過程 | 菊池 吉晃ほか |
| 運動の心的シミュレーションは,認知やイメージによる運動機能回復のためのリハビリテーションにおいて重要である.ここでは,脳磁界の解析によってその神経過程の時空間構造を明らかにする. | |
| 音楽療法の将来性 | 佐藤 正之 |
| 音楽療法の有効性の科学的証明は,始まったばかりである.それらの研究の一部を,自験例を含めて紹介した.今後はevidenceとしての対象症候,手法,評価法の確立が必要である. | |
| V.高次脳機能障害者に対する社会資源 | |
| 社会保険制度と障害者福祉制度の活用 | 生方 克之 |
| 高次脳機能障害者および家族への支援においては,医療,保険,福祉,職業に関する幅広い制度についての情報を本人の状況に即して提供することが必要である. | |
| 地域における高次脳機能障害者支援の実践 | 大坂 純 |
| 高次脳機能障害者を支援する会が運営する小規模作業所では回復の段階に応じてステップアップするlife modelリハビリテーションを実践している. | |
| 高次脳機能障害者に対する障害者職業センターの取り組み | 田谷 勝夫 |
| 日本における障害者職業センターの組織を解説し,ジョブコーチなど新しい高次脳機能障害者の就労支援の実態,問題点,展望について解説した. | |
| 家族会の組織とその役割 | 東川 悦子 |
| 高次脳機能障害支援モデル事業に課した役割と障害者自立支援法成立に伴う支援普及事業がどのように行われるか. | |

